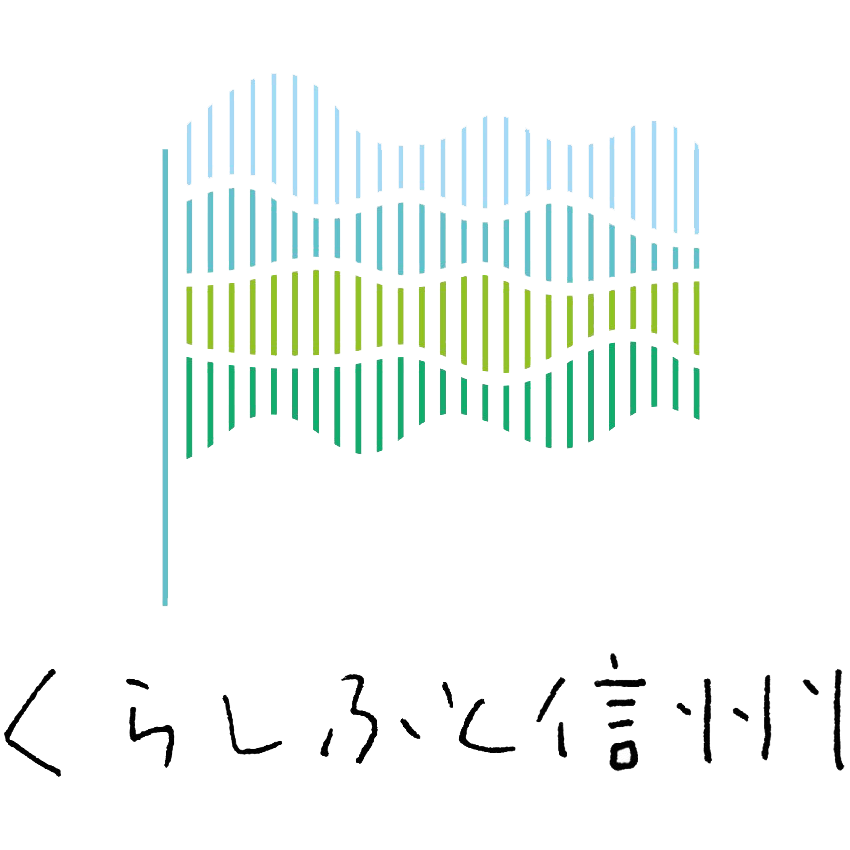【レポート】ゼロカーボンの取組の輪を地域ぐるみで盛り上げていきましょう!(大北地域ゼロカーボンミーティング)
令和6年1月26日に、大町市のサン・アルプス大町において「大北地域ゼロカーボンミーティング」を開催しました。第1部では基調講演及び取組事例紹介を、第2部ではパネルディスカッションを行いました。主な内容は以下のとおりです。
第1部(詳細はこちら)
【基調講演】
本県のゼロカーボン事業の普及にも長く携わっていただいている㈱地域計画建築研究所の黒崎さんから「ゼロカーボンに向けた取組を地域で盛り上げていきましょう」と題してご講演いただきました。
「行政主導」から「地域主導」で市民からアプローチすることの重要性を説明され、取組のヒントやアイデアをどのように生み出すかについてもご説明いただきました。



白馬高校の1年生3人が登壇。(浦野さん、岡本さん、デイリーさん)
「手がかじかむ教室を変えたい!」という先輩たちの思いを引き継いで、地域の協力なども得ながら生徒自らが教室を断熱改修した様子を語ってくれました。
今後は全ての教室を断熱したいという思いに、会場からも大きな拍手が沸き起こりました。
㈱レゾナック・グラファイト・ジャパン大町事業所からは稲田さん、村上さんが登壇。
水利権許可をベースに、地域の水を農業や発電用水に利用している水利システムの説明があり、またボイラー燃料を木質チップやLNGに転換することで、相当量の削減を実施しているとのご発言もありました。今後実施していく具体的な施策を説明しながら、削減見込みの数値も共有されました。
北アルプス森林組合の割田組合長からは、未利用木材や不要枝条の利用は乾燥が課題で、温泉熱や地熱、工場排熱などを利用するアプローチがあり、NEDOで採択された事業について説明がありました。教育面の重要性も説かれ、大学と共同して実施している体験型教育プログラムについても説明されました。
ゼロカーボンシティ宣言をされた大町市の牛越市長からは、大町市の現状や削減目標について共有され、市役所自ら実施している太陽光発電設備やEV化などを説明。市民への補助金などの支援や最新状況などが共有されました。
第2部(詳細はこちら)
【パネルディスカッション】
会場参加者にはあらかじめ座席にふせんを配布し、今行っている取組や登壇者への質問・応援などを記載していただき、パネルディスカッションで随時紹介するという、双方向型で進行しました。


地域での強みや課題について、登壇者からは水資源は豊富だが、里山整備や間伐材の利用が進んでいないといった意見や、環境を前面に出したサステナブル観光を推進すべきといった意見がありました。
また、会場からは森林組合に向けて、「バイオマス発電を推進する必要があると思うがいかがか」といった質問があり、「バイオマス発電は木材が限られてしまい、海外から適した材を運ぶと運搬時の温室効果ガス排出の観点からも、熱利用のほうが効率がいいと言われている。熱利用であれば、松くい虫の被害にあった支障木なども利用でき、地産地消も進むのでは」との回答がありました。


白馬高校1年生のみなさんからは、
・自分だけではなく、自分の子供達が住みやすい地域になれるよう、今後も環境問題に意識を持って行動する大人になりたい。
・将来都会に出ても戻ってきたいと思う地域になってほしい。都会にはない自然、雪がある地域のままであれば戻ってきたいと思う。
・環境問題とかを色々と意見を言うだけで何もしない大人にはなりたくない。
今の自分は行動できていないけれど、文句を言うぐらいなら行動できる大人になりたい
といった率直な意見をいただき、会場からは拍手があふれていました。

結びに、登壇者から一言ずつご発言がありました。
・森林組合からは自分がこれからの子供達、孫たちに何をすべきか、地域で何ができるか普段から考え行動することが大切であり、自身も中心になっていきたいとご発言がありました。
・㈱レゾナック・グラファイト・ジャパンからは、これまで「水」で地域のみなさんと繋がってきたが、これからは「木」による繋がりも持ち、森が健全な状態で次世代へと引き継がれていくよう、里山整備に参画するための調査を始めているとのご発言がありました。
・白馬高校生徒からは、学校で使用している灯油ストーブもCO2を排出していて、少しでも減らすために断熱改修もしながらストーブも変えてみたい、太陽光パネルにも興味がある。帰ったら校長先生に話してみたいといったご発言をいただきました。
これに対し、黒崎さんからは「協力してください」と声をあげれば、会場にいる方や地域・その知り合いの方が協力してくれると思う。ぜひ自分達だけで考えるのではなく一緒にやっていく発想で進めてもらいたいと激励がありました。
大町市長からは、ゼロカーボンという目標達成に向かって、行政・企業、事業者や市民の皆さんとも連携して、情報を共有し進めていく。将来世代に残す地域のことを中心に据えて考え、取り組んでいかなければならないと力強いお言葉をいただきました。
黒崎さんからは、環境省は「地域循環共生圏」を掲げ、厚生労働省では「地域共生社会」の実現を目指している。どちらも「地域」というキーワードが入っている。「地域」を切り口に豊かな社会、持続可能な社会をつくっていきましょう。こうした社会を実現するために、具体的に取組を始めていくことが大切です。
と締めくくられました。
キーワードは「地域」
まずは家族やお知り合い同士での共有から始まり、そこから小さな芽が出て、大きなうねりを生む、といった流れが生まれるよう、我々も取り組んでいきたいと考えています。